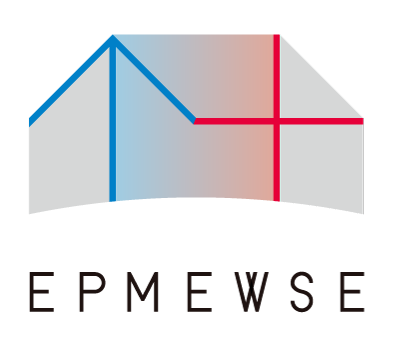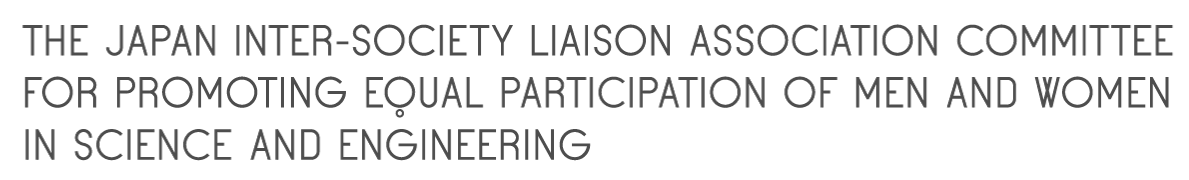Q&A
講演に寄せられた質問と、質問への回答をご紹介します。
折りたたみ
Q1
女性自身に社会から期待されている役割を果たそうとする行動がある。女性自身が、「女性だから●●」と考える文化が、特に日本は強い。このようなアンコンシャスバイアスは是正することが、長期的には良いのだろうか?
A1
これまでに「女性だから」という理由で、どれほど多くの能力が発揮されないままになってきたことでしようか? マチルダ効果のところでお話したのもその例です。
女性がもてる能力を十分に発揮し、組織でリーダー的な地位に就くことが当たり前の社会を目指すのであれば、無意識のバイアスの是正は必須です。
女性がもてる能力を十分に発揮し、組織でリーダー的な地位に就くことが当たり前の社会を目指すのであれば、無意識のバイアスの是正は必須です。
Q2
PTA等の活動で会長は男性がすべきという概念がある。その先入観を取ろうと苦労した。男性側は男性がすべきという先入観がある一方、女性側にも会長はやりたくないという無言の圧力がありました。どのように障壁を取り払っていけばよいのか?
A2
一番効果的であるのは、とにかく女性をその役につけることです。それによって女性にも務まることが分かりますし、男性でなければという概念が壊れていくと思います。女性がリーダー的な役目をやりたくない、同性にもさせたくないという意識を持つのは、PTAのみならず会社でもよくきく話です。この同調圧力は少しずつ実績を作りながら、変えていくことが出来ると思います。
Q3
アンコンシャスバイアスを向けられた対象者が、それと気付くことなく、あるいは気付いているが問題であることを認識することなく受け入れてしまうという現象についての研究等あれば紹介して欲しい。私は学生支援部門にいるが、『ガイコクジン(留学生)だから‥』『女の子なので・・』と、その当事者が無邪気に語る姿をこれまでもよく見てきたが、気になる現象ではあり、これをどう理解すればよいのかを考えている。
A3
自分に対する過小評価の問題ですね。まさにバイアスそのものです。壁があることに気づいていない場合も、壁を越える努力を放棄している場合もあると思います。その都度「なぜ、外国人だったら(女の子だったら)そうしなければいけないの?(あるいは、「そうできないの?」)と、問いかけることが最初の一歩だと思います。参考書としては“Promising Practices for Addressing the Underrepresentation of Women in Science, Engineering, and Medicine: Opening Doors ペーパーバック – 2020/3/19英語版 Rita Colwell (編集), Ashley Bear (編集), Alex Helman (編集)“(アメリカ科学アカデミー発行)が役立つかと思われます。
その他の推薦書としては、A5に挙げている 4) ステレオタイプの科学――「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは何ができるのか, クロード・スティール(著)、藤原朝子(訳), 英治出版 も優れた読みものです。
その他の推薦書としては、A5に挙げている 4) ステレオタイプの科学――「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは何ができるのか, クロード・スティール(著)、藤原朝子(訳), 英治出版 も優れた読みものです。
Q4
女性が常に一方的に不利益を被っているという文脈で話が進んでいるが、女性の男性に対するバイアスはないのか? 例えば男性が女性の容姿をからかうのは非難されるのに、その逆は相対的に受容されている。男性はこうしたことに耐えなくてはならない、というのも立派なバイアスだ。「女のくせに」というフレーズには反応するのに、「男のくせに」「男らしくない」と口に出す女性も非常に多い。
A4
女性の男性に対するバイアスも勿論あります。そして、それは、同様に抑制されるべきです。今回は、「人事採用や評価、賞の採択」等に働く「無意識のバイアス」について知っていただくのが目的でした。この場合、圧倒的に少数派の女性の側にどうしてもバイアスがかかってきます。そのことをご理解頂きたいと思い、そのような事例を準備しました。今回は割愛しましたが、医学部看護学科の男子学生の不安(例えば、将来、看護師として、オールド・ガールズ・ネットワークの中でうまくやっていけるか)は、同じ看護学科の女子学生の不安より、圧倒的に高いというデータがあります(2010年、日本大学参画推進室調査)。このことも、看護の世界にこれから入っていこうとする超少数派(この場合は男性)の持つ不安です。無意識のバイアスの問題は、単純に「男性vs.女性」の問題ではありません。少数派(マイノリティ)の側がもつ問題意識なのです。
Q5
無意識のバイアスについて、日本語や英語の読みやすい資料は?
A5
無意識のバイアスのコーナーのリーフレットとライブラリーをご覧ください。
【無意識のバイアスコーナー資料】
まず、以下のURL にしたがって連絡会HP、無意識のバイアスのコーナーのライブラリーに行ってください。リーフレットも簡便なので挙げておきました。
無意識のバイアス・リーフレット
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/leaflet.html
ライブラリー
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/doc/Unconscious_Bias_Library.pdf
ライブラリーのなかで役立ちそうなものを挙げました。
まず、以下のURL にしたがって連絡会HP、無意識のバイアスのコーナーのライブラリーに行ってください。リーフレットも簡便なので挙げておきました。
無意識のバイアス・リーフレット
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/leaflet.html
ライブラリー
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/doc/Unconscious_Bias_Library.pdf
ライブラリーのなかで役立ちそうなものを挙げました。
1) WORK DESIGN (ワークデザイン): 行動経済学でジェンダー格差を克服する
イリス・ボネット(著)、池村 千秋(訳)、大竹 文雄(解説)
NTT出版 2018/7/5発刊
ISBN-10 : 4757123590, ISBN-13 : 978-4757123595
イリス・ボネット(著)、池村 千秋(訳)、大竹 文雄(解説)
NTT出版 2018/7/5発刊
ISBN-10 : 4757123590, ISBN-13 : 978-4757123595
2) ポリモルフィア Vol. 3 (2018)
九州大学男女共同参画推進室編集委員会編
https://danjyo.kyushu-u.ac.jp/activity/index.php?r_mode=2&page2=2#cms_list_2
大坪久子:書籍紹介 『WHAT WORKS:Gender Equality by Design』by Iris Bohnet:上記のBohnetの著書のサワリの部分の紹介です。
まだ、日本語訳が出ていない時のものです。
九州大学男女共同参画推進室編集委員会編
https://danjyo.kyushu-u.ac.jp/activity/index.php?r_mode=2&page2=2#cms_list_2
大坪久子:書籍紹介 『WHAT WORKS:Gender Equality by Design』by Iris Bohnet:上記のBohnetの著書のサワリの部分の紹介です。
まだ、日本語訳が出ていない時のものです。
3) 女性リーダーが生まれるとき「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成
野村浩子 (著)
光文社新書2020/3/17発刊
ISBN-10 : 4334044638, ISBN-13 : 978-4334044633
野村浩子 (著)
光文社新書2020/3/17発刊
ISBN-10 : 4334044638, ISBN-13 : 978-4334044633
4) ステレオタイプの科学――「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは何ができるのか
クロード・スティール(著)、藤原朝子(訳)
英治出版 2020-04-06発刊
ISBN-10: 4862762875, ISBN-13: 978-4862762870
クロード・スティール(著)、藤原朝子(訳)
英治出版 2020-04-06発刊
ISBN-10: 4862762875, ISBN-13: 978-4862762870
5) 科学技術分野における男女共同参画:日本の持続的発展のために
Dilworth, Machi
Journal of the Society of Japanese Women Scientists, 20, 19?24 (2020)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjws/20/1/20_20003/_pdf/-char/en
Dilworth, Machi
Journal of the Society of Japanese Women Scientists, 20, 19?24 (2020)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjws/20/1/20_20003/_pdf/-char/en
6) 化学の世界にもっと女性リーダーを:米国の視点から
Celeste M. ROHLFING
化学と工業 72, 327?328 (2019)
https://www.chemistry.or.jp/opinion/ronsetsu1904.pdf
Celeste M. ROHLFING
化学と工業 72, 327?328 (2019)
https://www.chemistry.or.jp/opinion/ronsetsu1904.pdf
Q6
わかりやすく自分の置かれている状況に納得できるとともに、悲観的に思った。中学・高校の女性教員として「女性」側にできることはあるのだろうか?
A6
折角の総合大学附属学校です。その利点を生かされて、大学の教育学、心理学、社会学の先生がたも引き込んで、生徒の無意識のバイアスを減らすプログラム開発を計画なさってはいかがでしょうか? その中には、児童向けの「無意識のバイアスの絵本」の作成、実験劇を含む視聴型・参加型の教材開発、等も挙げられると思います。この過程で先生がたにも、今以上に、気づきと学びのチャンスがあるのでは・・。なお、実験劇はアメリカの大学でも「模擬人事選考委員会」等として取り入れられており、観客(この場合、研修受講者)は、どこで不適切な発言や行為があったかを指摘します。日本人の大人の場合、多少むつかしい点もあるでしょうが、それでも「よい研究者になろうと思ったら、結婚は△、出産はバツ」などと模擬審査員が述べたら、ブーイングは出るのではないでしょうか。児童に対しては児童用の劇が作れるかと思います。
資料:無意識のバイアスのもぐらたたき
資料:無意識のバイアスのもぐらたたき
Q7
初等中等教育現場でステレオタイプ・スレットを除く、また、マイクロアグレッションが発生しないための積極的な行動やグッド・プラクティスを知りたい。
A7
A6が参考になるかも知れません。ただ、この問題は、対大人でも、対子どもでも、その場ですぐに指摘することが一番です。あとから、どれだけ説いても当人には伝わらないと思われます。
Q8
女性の役職者や研究者を増やそうとすると、必ず「逆差別」でないかと議論が出てくる。それに対応する反論として、どのように対応すれば良いか?
A8
人類の5割は女性です。日本IBMの好事例で述べたように、残る5割の能力を引き出して活躍させることで、多様性のある組織を作ることは重要な戦略です。
それに関する好事例を添付します。
資料:女性の活躍は企業パーフォーマンスを向上させる
トップに決断していただくこと、トップにそう決断させること。女性理事の皆さんの出番ですね。名大の場合も、総長が、国連の“He For She”に選ばれたことが転換点になったと聞きます。国際的に宣言したわけですから、あとには絶対にひけません。ただ、そこまでの準備には複数の女性理事の皆さまと女性教員の方々の努力が大きかったと聞いています。
それに関する好事例を添付します。
資料:女性の活躍は企業パーフォーマンスを向上させる
トップに決断していただくこと、トップにそう決断させること。女性理事の皆さんの出番ですね。名大の場合も、総長が、国連の“He For She”に選ばれたことが転換点になったと聞きます。国際的に宣言したわけですから、あとには絶対にひけません。ただ、そこまでの準備には複数の女性理事の皆さまと女性教員の方々の努力が大きかったと聞いています。
Q9
マイクロアグレッションに該当する発言をしている人ほど本日のような研修に参加しないように思う。このような方々にはどのような働きかけをするべきなのか?
A9
強制的に参加していただくことしかないと思います。どうやって強制的に参加していただけるかについては、二つのやり方があると思います。
(1)A10の回答に記載しています。
(2)小規模の「義務づけられた」研修の実行。例えば、各人事委員会における選考審査前の研修もしくは確認作業の実施があります。この場合、数名の人事委員会ですから、委員長が各委員に強制できるはずです。研修後に理解できたかどうかの確認作業をして、「自筆の署名」をして委員長に提出、事務はその記録を残す。
資料:九大方式
勿論、その前に、全学あるいは各部局で、研修を義務化する必要があります。
これは、トップ(学長・部局長)のリーダーシップに依存します。
(1)A10の回答に記載しています。
(2)小規模の「義務づけられた」研修の実行。例えば、各人事委員会における選考審査前の研修もしくは確認作業の実施があります。この場合、数名の人事委員会ですから、委員長が各委員に強制できるはずです。研修後に理解できたかどうかの確認作業をして、「自筆の署名」をして委員長に提出、事務はその記録を残す。
資料:九大方式
勿論、その前に、全学あるいは各部局で、研修を義務化する必要があります。
これは、トップ(学長・部局長)のリーダーシップに依存します。
Q10
D&Iを推進する事業の長が、上記(マイクロアグレッションに該当する発言をしている人)のような場合、事業は形式的/制度的に最低限やっているだけになると思う。管理職など対象を限定した研修などが効果的なのだろうか?
A10
管理職限定の研修は、ある程度役立つとは思います。ただ、その場合、コンサル会社の一般的な講義では間に合わないでしょう。海外の先進的な大学、あるいは国内の先進的な大学の大学運営とD&I推進につて、同様の立場の方を講師としてお呼びになることです。競争心が湧くのではないでしょうか?
よい事例として名古屋大学の例を挙げさせていただきます。
よい事例として名古屋大学の例を挙げさせていただきます。
- 名大では、総長が、国連の女性活躍を推進する10大学(HeForShe)に選ばれ、関連の講演会を開くときは、総長から全教員に出席の圧力がかかり、男性の参加者のほうが多いそうです。
- 東大のKAVRIの大栗機構長が、名大に世界拠点機構運営に関する講演に来られた時、こちらも参加者は男性が多かった。大栗機構長はご自分が所属する海外の大学と比較して、日本の女性研究者に対する支援がいかに遅れているか、熱心にお話になった。世界のトップ男性研究者から、熱心に「日本が遅れている」と言われると、そこで初めて気づきがあるようです。
Q11
名古屋大学のトップダウンの事例紹介いただきましたが、他の日本の大学、中規模以上の私立大学でもトップダウンの取り組み事例はあるのか?
A11
名大ほどのトップダウンの事例はまだないとおもわれます。ただ、下記の内閣府男女共同参画局の取り組みが、その基盤になっていくのではないでしょうか。あきらかにその方向を目指しています。
内閣府男女共同参画局:輝く女性の活躍を加速する 男性リーダーの会「行動宣言」
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/index.html
内閣府男女共同参画局:輝く女性の活躍を加速する 男性リーダーの会「行動宣言」
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/index.html
Q12
「名伯楽」を育てるような実践・研究等はあるのか? あるいは,自然発生的な「名伯楽」を排除しない組織風土の条件とは?
A12
自然発生的な「名伯楽」を排除する組織風土とは具体的にどんなことでしょうか? よく、優れた教授のもとでは優れた研究者が育つと言いますが、これは真実だと思います。名伯楽を排除していては、育つべき若手もそだたないでしょう!?
Q13
企業などで、女性の内在性バイアスを取り除き、リーダーになりたいという意識を持ってもらうための仕掛けの例があれば教えて欲しい。
A13
男女共同参画学協会連絡会により2020年10月に開催されたたシンポジウムで、神崎夕紀氏(協和発酵バイオ株式会社常務執行役員)が紹介されたキリンホールディングスの多様性推進の取り組みが良い例ではないかと思います。
第18回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム(2020)報告書
https://www.djrenrakukai.org/doc_pdf/2020/18th_sympo_report.pdf
2014年に社長のイニシアティブの元、女性社員のネットワークがつくられ、ここからの提言をもとに社内制度をつくり上げることから始められたとのことです。女性リーダー育成推進のためのウイメンズカレッジの開講やメンタリングなどを行っておられますが、特筆すべき取り組みとしては、出産育児といったライフイベントを迎える前の若手女性に前倒しのキャリア形成を行って早目に仕事経験を与え、成功体験を積ませて得意領域を作らせることや、育児中も事情を鑑み「過剰な配慮」で戦力外のような働き方をさせないことがあります。このような取り組みで、2013年(4.2%)から2021年(12%)でリーダーの女性比率は約3倍に増加したとのことです。
第18回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム(2020)報告書
https://www.djrenrakukai.org/doc_pdf/2020/18th_sympo_report.pdf
2014年に社長のイニシアティブの元、女性社員のネットワークがつくられ、ここからの提言をもとに社内制度をつくり上げることから始められたとのことです。女性リーダー育成推進のためのウイメンズカレッジの開講やメンタリングなどを行っておられますが、特筆すべき取り組みとしては、出産育児といったライフイベントを迎える前の若手女性に前倒しのキャリア形成を行って早目に仕事経験を与え、成功体験を積ませて得意領域を作らせることや、育児中も事情を鑑み「過剰な配慮」で戦力外のような働き方をさせないことがあります。このような取り組みで、2013年(4.2%)から2021年(12%)でリーダーの女性比率は約3倍に増加したとのことです。
Q14
男女共同参画について学会がすべきことは?
A14
1.会員アンケート実行
1)女性のVisibility アンケート
資料:シンポジウム講演者選考と無意識のバイアス
資料:シンポジウム講演者選考と無意識のバイアス
2)女性の学会学術賞・奨励賞受賞割合の変遷と選考委員会の女性割合調査
3)学会大会参加断念の理由とその支援に関するアンケート(日本生理学会調査、2021)
http://physiology.jp/wp-content/uploads/2021/03/a098ebcf213480c6b4fffc7e817c9910.pdf
http://physiology.jp/wp-content/uploads/2021/03/a098ebcf213480c6b4fffc7e817c9910.pdf
4)大型予算申請を見送った理由の調査(JST調査)
参考データ:「研究開発プロジェクトダイバーシティを進めるためにーアンケート報告」
https://www.jst.go.jp/diversity/about/research/funding.html
特に、アンケートの主な結果(グラフ)が参考になります。
参考データ:「研究開発プロジェクトダイバーシティを進めるためにーアンケート報告」
https://www.jst.go.jp/diversity/about/research/funding.html
特に、アンケートの主な結果(グラフ)が参考になります。
・私は「選ばれる側にもバイアスがある」と話しましたが、チャレンジする前にその意欲を失う理由の中にこのような問題があるわけです。ここを解決することで、女性はもっと積極的にチャレンジするようになるはずです。
・チャレンジしたくても、出来ない理由をひとつひとつ洗い出すことです。コロナ禍で女性の論文数が減ったという報告がありますが、家事育児の負担が仕事の足を引っ張ったことは明白です。
2.この秋の連絡会大規模アンケートへの回答を宣伝すること、事後で、それぞれの学会のデータの解析をすること:ここで、解決すべき課題が見えてくるでしょう。
アンケートの結果を執行部、会員双方と共有すること。
アンケートの結果を執行部、会員双方と共有すること。
3.執行部に対して、アンケート等のデータに基づいて、何らかの要望・提言をすること、これがとても大切です。例えば、シンポジウムオーガナイザーと講演者の女性比率向上、学会賞受賞者の女性比率向上、役職及び委員の女性登用を積極的に進めるように執行部に働き掛けることも重要です。(アンケートはやってしまったら安心しますが、これが一番まずい!!)
Q15
学会運営における女性運営委員の比率向上にむけてのヒントは?
A15
1.学会の事情によっても事情が異なると思いますが、学会員の女性比率と女性運営委員の比率をほぼ同じにすることは、最低限の要件と思います。
このためには、会長や理事長といったトップから、理事や委員長へ女性委員任命のノルマを課すような働きかけが必要だと思います。
このためには、会長や理事長といったトップから、理事や委員長へ女性委員任命のノルマを課すような働きかけが必要だと思います。
2.また、各委員会に、できれば3人までの女性委員がいたほうが良いことは、これまでにも言われています。一人ではその女性の意見がすべての女性の考えと誤解されます。二人の場合、対立すれば、どちらかが意見をごり押しするか、ひっこめるか、二人とも黙り込むか・・。3名の場合、女性にも色んな考え方があって、「女だから」とひと括りには出来ない(女性は女性で多様である)ことがよく理解できると思います。
Q16
男女共同参画が進むにつれ、一部の女性に負担増(招待講演・参画委員・運営委員等々)となるが、良い解消方法はあるか?
A16
1.ことあるごとに、女性委員を増やしてくださいと女性委員自体がアピールすること。
2.若手(助教・講師レベル)でも、やる気のある人材を抜擢することです。
女性だからということだけで、忙しい女性教授・准教授をますます忙しくするよりも、広く適任者を入れることが、多様性の良さを発見できると思います。
女性だからということだけで、忙しい女性教授・准教授をますます忙しくするよりも、広く適任者を入れることが、多様性の良さを発見できると思います。
3.採用や昇進の際に業績として所属学会での活動を書かされることが多いので、若手、特に女性の若手にたいして、学会の中で活躍の場を準備することは、学会が配慮すべきこととしてとても大事なことだと思います。
Q17
ヨーロッパの学会では、LGBTに配慮して、No Gender へ移行中、男女で統計をとるのはおかしいのでは?
A17
国の施策の基本は統計調査にもとづいています。女性の可視化(ジェンダーギャップの可視化)にも統計資料を欠かすことは出来ません。
LGBTへの配慮のあまり、統計調査そのものを否定するのは、逆にLGBTの抱える問題を隠してしまうことになります。むしろ、統計にLGBTの欄をつくっても、あるいは申請書等の性別欄にLGBTと書いても、それによって不当な差別が生じないような啓発活動やシステム構築を目指したほうが建設的と思います。
LGBTへの配慮のあまり、統計調査そのものを否定するのは、逆にLGBTの抱える問題を隠してしまうことになります。むしろ、統計にLGBTの欄をつくっても、あるいは申請書等の性別欄にLGBTと書いても、それによって不当な差別が生じないような啓発活動やシステム構築を目指したほうが建設的と思います。
Q18
このような活動の男女比は女性に偏っているのでは? もっと男性がかかわる必要があると考えるか?
A18
1.勿論、男性にも積極的にかかわっていただきたいです。執行部の年代で、娘さんをお持ちの男性は、まず間違いなく、すぐに理解してくださいます(娘と孫の幸せを自然に考えられます)。
2.ジェンダーギャップの問題は女性の問題であると同時に男性の問題でもあります。
Q19
講演の中で 男女共同参画とAccountability という言葉が出てきたが、何を意味するのか? 少し詳しい説明が欲しい。
A19
ここではAccountability という言葉を、「研究者の科学と社会に対する責任」という意味で用いています。したがって、男女共同参画とは、これまで男性が担って来た「科学と社会」に対する役割と責任を女性も担うということ、です。具体的には、大学・研究機関の運営の役割と責任を同等に負うという意味で用いています。
Q20
自分が女性だからという理由で役職に選出されたり、採用されたりするのはそれもまたコンプレックスの原因になるのでは?と思いましたが、いかがでしょうか。
A20
コンプレックスを持つ必要は全くありません。役職に選ばれた場合、むしろ、あなたの能力発揮の場が与えられたと考えるべきです。これまで、男性の視点で運営されてきた大学や部局に新しい視点を吹き込むことが出来る大きな機会なのです。女性限定公募で採用された女性研究者からこの声を聞くこともありますが、私は遠慮なくそのポジションをゲットするべきと考えます。研究者としてのスタートはポジションあってこそ、始まるのです。一般公募であれ、女性限定公募であれ、そのチャンスをつかむべきです。ポジションを得た後で業績を上げれば良いだけのことです。
Q21
男女共同参画の本筋から少し逸れてしまうかもしれませんが、男女に二分化できるものなのでしょうか? 男性、女性などという概念にこだわりすぎない多様性が認められるべきなのではないか、と考えます。
A21
人類の50%が女性です。その能力をまず生かすことを考えてください。それで、社会に多様性が生まれます。女性が直面する課題において不平等が是正されないかぎり、他の場合にも是正はされないことでしょう。
Q22
育児をする、しないにかかわらず女性が不利になる場合がある、というお話には納得しましたが、男性が一括りになっていたのが気になりました。調べられていないのか、育児をする男性がそもそもいないのか、どちらでしょうか? もし後者であれば、男女の分業をとっぱらうための職場環境改善が必要かと思いました。
A22
男女を分けたグラフをご覧ください。グラフからおわかりのように、性別分業は、可能な限り、とりはらうべきだと考えます。男姓、女性以外のわけ方で(例えば、LGBTQ 対男性(あるいは女性)間の問題で、不公正なことがある場合、考えるべきとは思いますが、私たちは今のところ、人類のほぼ50%を占める女性の能力が十分に発揮できていないことをまず問題としています。
Q23
質問というか疑問ですが、講演の際に女性が学会に入り研究者として活動していくことで、全体的な研究活動の向上や社会への貢献となるという話がありました。その際に女性からの知見や見方が必要となるとし、いくつかの例も挙げて下さりよく理解出来ました。勿論それが現代の問題であり解決すべき事ですし、女性の参加率(言葉が間違っていたら申し訳ないです)が高まるほど快方に向かうと思います。ですが、女性が増えることで問題解決になることでは無いと思いますし、それを女性が担わないといけないと、講演を聞いていて感じました。この問題は人類全体の問題と言うべきといいますか、女性・男性の性別関係ない話だと思います。ですので、そこでの女性が必要とされている、参加しないといけないことには変わりないのですが、問題を解決していくために必要という考え方はある種女性へのバイアスとなってしまうのかが疑問になりました。
A23
現状は性別(主に男性)や社会的境遇が同質の偏った人達の視点から文化、習慣、技術、社会インフラが作られているために、歪みがでています。そのような歪みをただして行くためには、異なる視点および当事者の視点を持った、さまざまな人々がさまざまな組織に参画する必要があります。したがって、女性の参画が進んでいない分野では、女性がもっと参画する必要があるのです。講演で触れたジェンダード・イノベーションは最も分かりやすい例です。車のシートベルトの設計や薬の開発において、性差を無視して男性型のダミーや雄の実験動物だけを使って研究・開発された製品に深刻な欠陥があったことは有名な例です。日常的に身の回りにある道具、機械、構造物、建造物などの多くが健常な男性デフォルトの仕様となっており、それに適合しない多くの人に不自由や不具合を強いています。キャロライン・クリアド=ペレス著の「存在しない女たち: 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く」( 神崎朗子(翻訳)河出書房新社2020/11/27発刊ISBN-10: 4309249833, ISBN-13: 978-4309249834)には、そのような「男性デフォルトの社会」の現実が非常にわかりやすく解説されています。
もう一つ大事なことは、女性の参画が進んでいない分野では、女性の潜在能力が生かされていないという点です。知的な分野で男女の潜在能力に差はありません。女性が参画すればより多くの人材の中から、より適合した人材が選ばれて活動することになり、全体のレベルが上がります。また、多様性が増すことで、集団の個々の能力が高められることが社会心理学の研究で明らかにされています。
もう一つ大事なことは、女性の参画が進んでいない分野では、女性の潜在能力が生かされていないという点です。知的な分野で男女の潜在能力に差はありません。女性が参画すればより多くの人材の中から、より適合した人材が選ばれて活動することになり、全体のレベルが上がります。また、多様性が増すことで、集団の個々の能力が高められることが社会心理学の研究で明らかにされています。
Q24
ジェンダーバイアスの固定観念を徐々に改善していくことが望まれますが、組織の改革、意識改革が必要であるとわかりました。具体的にどのような改革方法が効果的だと考えられますか? 私は各々の家庭という組織内での男女差の意識の再認識が有効かと思いました。先生の意見をお聞きしたいです。
A24
たしかに家庭の中の意識改革は重要ですが、その困難さは世代間にわたるので、大変なものと思います。大学や社会が変わることで、家庭の意識が変わることが、むしろ期待されます。例えば、設立したての奈良女子大の工学部は、前期の倍率が6倍以上あり、理学部の2-3倍より高倍率だったそうです。これも大学が変わって初めて保護者や受験生の意識が変わった好事例ではないでしょうか?
https://www.keinet.ne.jp/exam/entry/1330.html
来年度スタートのお茶の水女子大学の工学部も、共創工学部ということで、半分文系、半分理系教員が集められているそうです。女子大学に工学部を、と言う実装はもっとはやく実現しておくべきことだったのかも知れません。
https://www.keinet.ne.jp/exam/entry/1330.html
来年度スタートのお茶の水女子大学の工学部も、共創工学部ということで、半分文系、半分理系教員が集められているそうです。女子大学に工学部を、と言う実装はもっとはやく実現しておくべきことだったのかも知れません。
Q25
私たちの世代だと、今のところマイクロアグレッションはあまりないように感じます。ひとつ疑問があります。組織リーダーの望ましさには例えばどのようなものがあるのでしょうか。わたし的には話が聞ける女性的な考えと、進んで行動し責任を取る、という男性的な考えが両方必要だと感じました。
A25
今回はお話しなかったスライドで、重要なものがあります。元日経ウーマン編集長、野村浩子さんの調査(日本の上場企業25社の幹部と幹部候補生1500人対象)です。リーダーの特性として10項目の特性が挙げられています。(出典:「組織リーダーの望ましさとジェンダー・バイアスの関係― 男女別、階層別のジェンダー・バイアスを探る」野村 浩子、川﨑 昌 淑徳大学人文学部研究論集第4号, 2019) 1)リーダーの能力がある、2)責任感が強い、3)行動力がある、4)説得力がある、5)目標へ強いコミットメント、6)率先して行動、7)プレッシャーに強い、8)ビジネスセンスがある、9)自立している、 10)能力が高い。このうちの5個(1, 2, 3, 4, 6)が男性の望ましいステレオタイプと重なります。女性の望ましいステレオタイプとは2個(2, 9)しか重なりません。ただし、注意していただきたいことは、このリーダー像は「日本の上場企業25社のトップとトップ下の考え」であるということです。この考え方自体に無意識のバイアスがあると考えたほうがよいと思います。さらに、男性あるいは女性の望ましいステレオタイプにも無意識のバイアスが含まれています。「調整的である」ことは、野村氏のリーダー像にも男性のステレオタイプにも女性のステレオタイプにも、上位10位までには含まれてはいませんでした。ただ、私は女性で初めての南極越冬隊夏隊の女性隊長さんが「私は調整型」とおっしゃったのを聞いたことはありますが、これは彼女の自然な資質であって、女性だから調整型というわけではないように思います。男女にかかわらず、調整型であっても、トップは常に決断を下し続けなければならないのですから。
なお、地位や業績などの利害が少ない集団では、マイクロアグレッションはあまり目立たないかもしれません。しかし、職場のような強い利害が絡む組織では、女性やマイノリティーの人々に対するマイクロアグレッションは起こりがちで、これが高じると深刻なハラスメントになります。日本社会には、ハラスメントの被害者側にも問題があるというバイアスが往々にしてあり、組織は人間関係を表面上穏便に保つことを重視するために、これまで多くの被害者が我慢したり泣き寝入りしてきました。大学でも企業でも、どの組織でもハラスメントは決してなくならない深刻な問題です。そのため、どの組織にもハラスメント対策の相談窓口の設置や体制構築が求められています。
なお、地位や業績などの利害が少ない集団では、マイクロアグレッションはあまり目立たないかもしれません。しかし、職場のような強い利害が絡む組織では、女性やマイノリティーの人々に対するマイクロアグレッションは起こりがちで、これが高じると深刻なハラスメントになります。日本社会には、ハラスメントの被害者側にも問題があるというバイアスが往々にしてあり、組織は人間関係を表面上穏便に保つことを重視するために、これまで多くの被害者が我慢したり泣き寝入りしてきました。大学でも企業でも、どの組織でもハラスメントは決してなくならない深刻な問題です。そのため、どの組織にもハラスメント対策の相談窓口の設置や体制構築が求められています。
Q26
今回のセミナーの内容に関心のない人達へ、私達ができることはないでしょうか? 他人の意識を変えることはとても難しいと思います。私達が具体的にすぐに取り込めるジェンダーバイアスの取り組みとしては、どのようなことがあるでしょうか。
A26
発言者に面と向かって「それはバイアスですよ」と注意することは、勇気がいりますし、人間関係が悪くなって自分に不利になることも考えられます。まずは、気の置けない周囲の人たちに分かりやすい研修資料を薦めて見てもらい、バイアスについて言語化された知識を持ってもらうことから始めてはいかがでしょうか。多くの人は確固たる信念としてではなく、それまで育ってきた環境で刷り込まれた常識として無意識のバイアスを持っていますから、研修を受けるだけで見方が変わることが多くあります。男女共同参画学協会連絡会のホームページの「無意識のバイアスのコーナー」には、簡潔に説明したリーフレットや短時間で視聴できるビデオが提供されています。是非ご利用ください。
Q27
本日の講演で、女性でも学生や若いうちはあまり男女の差を感じないが、キャリアと年齢を重ねてさまざまな問題と向き合う中で、男女共同参画の取組みの重要性を理解するようになる、というお話がありました。自分自身、楽しく仕事をしているのは間違いありませんが、一方で苦労することが多い状況です。女子学生も比較的多くいるので、あまり大変な現実を見せるよりは楽しい面を見せたいと心がけていますが、それでいいのだろうかと迷うこともあります。「ガラスの天井なんてもうないんじゃないですか」などと言う学生に、なんと答えたらいいのでしょうか。
A27
「ガラスの天井なんてもうないんじゃないですか」ときく学生さんには、天井があることを伝えるべきです。それは決して愚痴や弱みにはなりませんし、彼らが社会に出てからの備えになります。
Q28
私はアメリカに長く留学していましたが、もし今のアメリカでこのポジションは女性だけです、男性だけですという公募が出たら、間違いなく問題になると思います。CVにも性別や証明写真はいらないので、業績と研究のプレゼンで評価される公平な(人種に対するracismはありますが)採用プロセスが出来上がっていると思います。そして欧米はすでに日本のような問題をクリアしたからこそ、今のステップに進めている、日本が大きく遅れていることは実感しております。欧米では研究者の比率を上げるために、日本のような施策はおこなったのでしょうか?また、現在の日本の施策は欧米の方からどのようにみられているのでしょうか?
A28
アメリカの場合、大元に公民権法がありますから、それに基づいた人種・皮膚の色・宗教・性別・出身国による雇用の差別禁止の法律や条項は多々あります。雇用の差別については、以下を参照ください。
https://www.findlaw.com/employment/employment-discrimination/title-vii-of-the-civil-rights-act-of-1964-equal-employment.html
米国も一足飛びに履歴書に写真なし、性別なしになったとは思いません。いつごろからその制度が定着したのか、調べる必要があります。少なくとも2012年発表のMoss-Racusin et al. PNAS, 109,16474-16479 (2012) の時点までは男性名、女性名で中身は同じ履歴書をつかったゴールドバーグ・デザイン型の調査が生きていたわけです。(TAの採用やメンターは女性教員でも男子を優先)人事選考の場合、写真なし、性別なしの応募書類が使用されるのは第一次の書類審査までです。二次審査以上の場合、研究室のホームページの閲覧や本人に面接することで、写真や性別に関する情報はほぼ得られます。そこにバイアスが入る余地はあるかも知れません。ただし、重要なことは、性別に関係なく優秀な人材を採用することが目的であります。優れたな研究ができそうな人を採用しないと、昇進できずやめてもらうことになりますので、その方が部局にとっては痛手となります。
オランダのEindhoven University of Technologyで最初の6か月間は女性の応募者しかうけつけず(女性先行公募)、その期間に女性の応募者がなかった場合だけ男性の応募も受け付けるという公募をやっているというNatureの記事があります。この中には、ヨーロッパの他の国の例もすこしのっています。もっと探せば見つかるかもしれません。「How a Dutch university aims to boost gender parity Female applicants will receive priority consideration for faculty positions at Eindhoven University of Technology for at least 18 months.:Nature career news 25 June 2019」https://www.nature.com/articles/d41586-019-01998-7
上記の記事の中にはドイツのマックス・プランク協会が女性限定公募を始めたという記載もあります。ドイツの場合、女性が少ない分野や部局では、女性が意図的に採用されている事例もあると聞きました。ヨーロッパでは必ずしもアメリカ型の人事選考が取られているわけではないと思います。
なお、現在の日本の施策は、日本が必要だと考えるから取っているわけで、外国からどう見えるかは、気にする必要はないと思います。少なくとも講演でおはなししたように、法的に問題はなく、法律より上位規範である国際条約でも認められている特別措置です。ちなみに、国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解(2016年2月16日)において教育に関して、
(a) 進路に関する相談活動を強化し、女子が伝統的に進出してこなかった専攻(STEM)を目指すよう奨励するとともに、女子が高等教育を修了する重要性について教員の意識啓発を行うこと、
(b)女性教授の数を増やすとともに、教育部門の上位の管理職や意思決定を行う地位への女性の参画を拡充するため、暫定的特別措置を含む具体的方策をとること、
を締約国(日本)が行うよう勧告しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156147.pdf(日本語仮訳)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000133481.pdf(英語)
https://www.findlaw.com/employment/employment-discrimination/title-vii-of-the-civil-rights-act-of-1964-equal-employment.html
米国も一足飛びに履歴書に写真なし、性別なしになったとは思いません。いつごろからその制度が定着したのか、調べる必要があります。少なくとも2012年発表のMoss-Racusin et al. PNAS, 109,16474-16479 (2012) の時点までは男性名、女性名で中身は同じ履歴書をつかったゴールドバーグ・デザイン型の調査が生きていたわけです。(TAの採用やメンターは女性教員でも男子を優先)人事選考の場合、写真なし、性別なしの応募書類が使用されるのは第一次の書類審査までです。二次審査以上の場合、研究室のホームページの閲覧や本人に面接することで、写真や性別に関する情報はほぼ得られます。そこにバイアスが入る余地はあるかも知れません。ただし、重要なことは、性別に関係なく優秀な人材を採用することが目的であります。優れたな研究ができそうな人を採用しないと、昇進できずやめてもらうことになりますので、その方が部局にとっては痛手となります。
オランダのEindhoven University of Technologyで最初の6か月間は女性の応募者しかうけつけず(女性先行公募)、その期間に女性の応募者がなかった場合だけ男性の応募も受け付けるという公募をやっているというNatureの記事があります。この中には、ヨーロッパの他の国の例もすこしのっています。もっと探せば見つかるかもしれません。「How a Dutch university aims to boost gender parity Female applicants will receive priority consideration for faculty positions at Eindhoven University of Technology for at least 18 months.:Nature career news 25 June 2019」https://www.nature.com/articles/d41586-019-01998-7
上記の記事の中にはドイツのマックス・プランク協会が女性限定公募を始めたという記載もあります。ドイツの場合、女性が少ない分野や部局では、女性が意図的に採用されている事例もあると聞きました。ヨーロッパでは必ずしもアメリカ型の人事選考が取られているわけではないと思います。
なお、現在の日本の施策は、日本が必要だと考えるから取っているわけで、外国からどう見えるかは、気にする必要はないと思います。少なくとも講演でおはなししたように、法的に問題はなく、法律より上位規範である国際条約でも認められている特別措置です。ちなみに、国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解(2016年2月16日)において教育に関して、
(a) 進路に関する相談活動を強化し、女子が伝統的に進出してこなかった専攻(STEM)を目指すよう奨励するとともに、女子が高等教育を修了する重要性について教員の意識啓発を行うこと、
(b)女性教授の数を増やすとともに、教育部門の上位の管理職や意思決定を行う地位への女性の参画を拡充するため、暫定的特別措置を含む具体的方策をとること、
を締約国(日本)が行うよう勧告しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156147.pdf(日本語仮訳)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000133481.pdf(英語)
Q29
欧米では無痛分娩のため母体の体力を極力保ったまま、お産をコントロールしています。そのため母親も出産の前後2週間ほどの休みで仕事に復帰しています。日本でも無痛分娩を広げて、キャリアのギャップが出ないようにする施策は必要だと思いますか?
A29
無痛分娩のお話ですが、たしかに日本はお産の中で無痛分娩率は8.6% (2020年)と高くはないですね。しかし、これは本人の希望によるもので、強制はできません。第一子の場合、出産前日までラボにいたと言う女性は米国では多いと思います。私もそうでしたが、ただ産後の状況はこれも産婦ごとに違いますので強制は出来ません。ラボに出かけて実験をするのも大切でしょうが、キャリアに穴を空けないように、論文執筆、総説執筆、データのまとめ、同僚とのdiscussion、研究費申請等々やることは多々あるはずです。実験動植物のお世話なども上手に代替者をおくことの方が大切と思いますが。
Q30
日本社会の問題を考えると絶望的な気分になります。欧米でも日本と同じような問題がありましたが、解決に向けた取り組みがされて、日本は取り残されてしまいました。日本の国民性というのかわかりませんが、性差別や格差を良しとする社会のムードをなんとかするにはどうしたらいいのでしょうか。漠然とした質問ですみません。
A30
「学会としては、もっと一般社会向けに科学の成果や面白い話を講演するイベントを積極的に実施して、そこで女性の研究者を露出していくといった取り組みや、女子学生向けに就職先のマッチングイベントをすることなどが考えられます」が、この回答に対してはもういやというほどオープンキャンパスや夏学でやったという声が聞こえてきそうです。要は、保護者を教育しなければなりません。それも多くの場合、母親を・・。特定非営利活動法人Waffle(https://waffle-waffle.org/about/)のような、自分たちの娘よりほんの少し年長の女性のロールモデルを見せるのが一番でしょうね。
Q31
シンポジストの男女比の調整など、学会として取り組むべきことが明確になり、有意義なセッションだったと思いました。男女共同参画連絡会が主体となって、各学会の主催講演会のスピーカーの男女比を「見える化」して改善を促すと日本の科学がよい方向に向かうかもしれません。
A31
ご提案ありがとうございます。男女共同参画学協会連絡会では、最近の5年間(2017~2021)における加盟学会におけるシンポジウム・ワークショップ等の「オーガナイザーの女性比率、講演者の女性比率等の調査報告をしています。どうぞ、下記をご覧ください(2022年学協会連絡会加盟学会の活動調査, 図22~ 25)https://djrenrakukai.org/doc_pdf/2022/2022_activity_report.pdf
残念ながらオーガナイザーの女性比率はまだ10%台で高くはありませんが。
残念ながらオーガナイザーの女性比率はまだ10%台で高くはありませんが。
Q32
主に選考する側とされる側がもつバイアスについてのご講演内容でしたが、家族や親類あるいはさらに外野にいる人がもつ「男のくせに」「女のくせに」といった色眼鏡の声に疲弊する研究者もいます。こうした社会に根をはるバイアスを低減するには、学会としてどのようなアプローチが可能なのでしょうか。有効策のアイデアがあればご教授いただきたくお願い申し上げます。
A32
ここでは先にA26で答えた回答を再掲したいと思います。まずは、気の置けない周囲の人たちに分かりやすい研修資料を薦めて見てもらい、バイアスについて言語化された知識を持ってもらうことから始めてはいかがでしょうか。多くの人は確固たる信念としてではなく、それまで育ってきた環境で刷り込まれた常識として無意識のバイアスを持っていますから、研修を受けるだけで見方が変わることが多くあります。是非、研修前と研修後にアンケートを取ってみてください。案外、前後で意識がかわっているものですよ。男女共同参画学協会連絡会がホームページの「無意識のバイアスのコーナー」には、簡潔に説明したリーフレットや短時間で視聴できるビデオが提供されています。是非ご利用ください。
Q33
公募を女性国際限定5人にしたところ応募者が増えたというお話で質問があります.
- (1)同じ組織の同じ公募で変えたのでしょうか.
- (2)要因については女性だけでなく,国際と複数が追加されています.どの組織でも出来る公募ではなく,同じ様にするには今まで個々に公募していたところを,同時に女性限定として一斉公募で出せばよい,ということになりますでしょうか.
- (3)一方,女性1人の限定公募では応募者ゼロか該当者なしの場合があります.地方は特にそうです.この問題について解決策をお聞かせいただければと思います。
A33
まず、(1)と(2)についてお答えします。
ここで私(大坪久子)が挙げた例は九州大学の女性限定・国際公募の事例です。この場合、理工農が中心ですが、全学が対象とされた国際公募です。2段階選抜で、第一次選考は各部局における書類審査、第2次選考は、全学の審査委員(評議員会+外部評価委員)が10数名で、推薦されてきた候補者と担当部局長のプレゼンを受けて、質疑応答をします。詳細は省きますが、その結果を投票で判断して採用者が決まる仕組みです。
(追加情報)
九州大学の女性枠のホームページ:
年数も経ったことから昨年閉鎖されたそうです。
講演などで説明に使うスライドの中でHP上で見られるのはポリモルフィアの最新号(Vol.8)の玉田副学長の文章に挿入されたスライドがわかり易いのでそちらをご覧ください。p.23 の左側の下の図となります。
https://danjyo.kyushu-u.ac.jp/activity/index2.php?r_mode=2
(3)につきましては、地方の大学では特によく聞く言葉です。
ただ、良い候補者がいない、応募者がいない、となったときに、次の一手をどうするかということが重要です。
どうぞ、改善の余地を探してくださいますように。
ここで私(大坪久子)が挙げた例は九州大学の女性限定・国際公募の事例です。この場合、理工農が中心ですが、全学が対象とされた国際公募です。2段階選抜で、第一次選考は各部局における書類審査、第2次選考は、全学の審査委員(評議員会+外部評価委員)が10数名で、推薦されてきた候補者と担当部局長のプレゼンを受けて、質疑応答をします。詳細は省きますが、その結果を投票で判断して採用者が決まる仕組みです。
(追加情報)
九州大学の女性枠のホームページ:
年数も経ったことから昨年閉鎖されたそうです。
講演などで説明に使うスライドの中でHP上で見られるのはポリモルフィアの最新号(Vol.8)の玉田副学長の文章に挿入されたスライドがわかり易いのでそちらをご覧ください。p.23 の左側の下の図となります。
https://danjyo.kyushu-u.ac.jp/activity/index2.php?r_mode=2
(3)につきましては、地方の大学では特によく聞く言葉です。
ただ、良い候補者がいない、応募者がいない、となったときに、次の一手をどうするかということが重要です。
- まず、選考委員会には「人事選考委員会用チェックシート」はありますか?
- 選考委員会前に、委員長と委員は「無意識のバイアス」に関する講習が義務づけられていますか?
- 公募期間を延長する(これは、国内でもよく行われています。オランダなどでは、半年間「女性先行公募」をして、女性が来ないときには一般公募にする。https://www.nature.com/articles/d41586-019-01998-7
- 国内外の関連学会を通じて優れた女性研究者を探す。そのようなネットワークを常時強化しておく。
- 研究者を惹きつけるだけの両立支援制度(インフラ・帯同雇用制度・立ち上げ資金措置・メンター制度等)が整備されているかのチェック。
どうぞ、改善の余地を探してくださいますように。
Q34
- (1)バイアスが正しく働いている場合も,バイアスを取り除くべきか?
バイアスが良い方向に働いている時はバイアスに気づいていないだけなのでは? - (2)現代のバイアスへの行き過ぎた配慮は逆バイアスを生むのでは?
- (3)男女に関して「良いバイアス」というものはあるのでしょうか.個人的にはあるような気がします.私の父が家でよくする話を書かせていただきます.父は会社からお茶くみ・掃除は女性社員の仕事ではないとよく言われるそうで,性別に関わらずそれらの仕事を行うようになったそうです.
- (4)しかし,重い荷物は男性のみ運ぶそうです.単純に男性の方が仕事量が違うと不満を言っています.私は父が言っていることは心が小さいなと思いつつ一理あるなと思いました.このような性別による能力の差から同じことができない場合はどうすればいいですか.これは区別ではないのか?と思っています
- (5)昇進の機会自体の制度は平等にあったとしても,なかなか踏み出せない部分もあると思う.選択肢の1つとして自然に考えられるようになるためにはどうすれば良いか知りたいです.
A34
この方の質問を、(1)~(4)と(5)に分けて考えました。
(1)~(4)について:
まず言えることは、「バイアス」の定義が曖昧、もしくは誤っているのでは、ということです。同時に良いバイアスとはどのようなことか?
私たちがいう「無意識のバイアス」は、それがあるゆえに「本来持っているその人の能力が発揮されない後天的な思い込み」のことです。例えば、能力はあるのに女性だから、母親だからという理由で採用されなかった、等々です。その人の属性故に能力を否定されるのはおかしいとは思いませんか? 男性は筋力があるから、重い荷物をもつ、女性は重い荷物を持てないからお茶汲みをする!?? 荷物は持てる人が持てばいいし、お茶だって男性も上手に入れられるはず。
(5)について:
機会が準備されていてもなかなか踏み出せないということは、十分にありうることです。
自分自身への自己評価が低い、周囲が足を引っ張る等のジェンダーバイアスは強いものです。
ロールモデルが増えて、私もやれるのだという安心感が醸成されること、背中を押すメンター(名伯楽)がいること、何より周囲がその人を支えようとする環境を作ることが大切です。これは、個人の努力だけでは不可能なことです。部局と執行部、つまりリーダーの役割です。
参考資料として以下の資料も挙げて起きます。
DEIの考え方を端的に示す図です。
大人と少年と幼児が野球場の外から中をのぞき見しています。DEI(Diversity-Equity-Inclusions)の考え方では、3人とも中を覗けるように、段差の違った踏み台を提供します(Equalityの場合、同じ高さの踏み台を提供)。
参考になるとよいのですが・・。
(1)~(4)について:
まず言えることは、「バイアス」の定義が曖昧、もしくは誤っているのでは、ということです。同時に良いバイアスとはどのようなことか?
私たちがいう「無意識のバイアス」は、それがあるゆえに「本来持っているその人の能力が発揮されない後天的な思い込み」のことです。例えば、能力はあるのに女性だから、母親だからという理由で採用されなかった、等々です。その人の属性故に能力を否定されるのはおかしいとは思いませんか? 男性は筋力があるから、重い荷物をもつ、女性は重い荷物を持てないからお茶汲みをする!?? 荷物は持てる人が持てばいいし、お茶だって男性も上手に入れられるはず。
(5)について:
機会が準備されていてもなかなか踏み出せないということは、十分にありうることです。
自分自身への自己評価が低い、周囲が足を引っ張る等のジェンダーバイアスは強いものです。
ロールモデルが増えて、私もやれるのだという安心感が醸成されること、背中を押すメンター(名伯楽)がいること、何より周囲がその人を支えようとする環境を作ることが大切です。これは、個人の努力だけでは不可能なことです。部局と執行部、つまりリーダーの役割です。
参考資料として以下の資料も挙げて起きます。
DEIの考え方を端的に示す図です。
大人と少年と幼児が野球場の外から中をのぞき見しています。DEI(Diversity-Equity-Inclusions)の考え方では、3人とも中を覗けるように、段差の違った踏み台を提供します(Equalityの場合、同じ高さの踏み台を提供)。
参考になるとよいのですが・・。
Q35
評価にバイアスがあるだけではなく,評価基準の設定そのものにバイアスがある気がする.
A35
その通りです。末尾に参考までに2枚のスライドを挙げました。
メリトクラシー(Meritocracy)の陥りやすい罠と人事選考のチェックシートです。
メリトクラシーは能力主義・実力主義と理解されていますが、その実力の有無、高低がどのように決められたかが問題ということです。
チェックシートは、上に挙げたQ33−35への回答のひとつでもあります。
メリトクラシー(Meritocracy)の陥りやすい罠と人事選考のチェックシートです。
メリトクラシーは能力主義・実力主義と理解されていますが、その実力の有無、高低がどのように決められたかが問題ということです。
チェックシートは、上に挙げたQ33−35への回答のひとつでもあります。
Q36
ジェンダーや人種等に関する無意識のバイアスについて,実験に基づいた学術論文を引用しながら示していただき,とても分かりやすかったです.私個人(40代女性)は,これまでのキャリアにおいて女性であることによって,理不尽な差別や大きな不利益を受けた経験はあまり無いと認識しています.またその一方で,仕事の現場に女性の研究者が少ない現状が依然としてある中で,自分自身もマイノリティ意識や孤独を抱えながら働いてきたことに今回のお話で気がつき,涙が出そうになりました.
A36
女性が少ない中で仕事をしていると、自分が女性であることも、孤立していてネットワークも持っていないことも忘れてしまいがちですね。気づいたときには、働き方も仕事第一、仕事が全てになって、自分が上司になっても、部下に同様の働き方を期待することもありがちです。これであっては、若手の育成も多様性の確保も期待できません。よいネットワークを育てて下さいますように・・。
Q37
男女共同参画は大切だと思うが,女性限定採用が正しい道なのかは分からない.
A37
これまでに、若手の新規採用者の女性比率は、どの分野においても博士課程修了者の女性比率を大幅に下回ってきました。つまり、日本では男性を優先的に採用する極端な人事が常態化している、という現実があります。女性限定人事は、この状況を是正するための特別措置として行われています。暫定的な経過措置ということをご理解下さいますように。
Q38
女性が出産・育児をしながら働く環境づくりは進んでいる.しかし.男性が家事・育児をしながら働く環境づくりは遅れている.家事・育児をしたい男性もいる!!
A38
女性の社会参画には男性の家庭参画がキーポイントですね。それを担保するシステムを作ってください。これも、個人の努力だけでは不可能なことです。部局と執行部、つまりリーダーの役割です。
Q39
女性のキャリア形成は多様で、研究を推進できる年齢も様々になっています。それにも関わらず、昇進やチャンスを獲得するための年齢が限られていますので、その年齢を逃すと、経験の差から将来の先がなくなることを実感しています。……中略……日本の大学や一般企業では教員やマネジメント以外道がなくなる気がしています。男女とも研究者が年齢性別なく、総力をあげて研究を推進するために協力しあう、切磋琢磨するような体制ができれば、安心して研究者になることができるのではと思いました。海外の事例では、いかがでしょうか?
A39
日本は、従来の家族制度やそれを支える意識が色濃く残り、そのために家事、育児、介護といった無償のケア労働が非対称に女性に重くのしかかっている社会です。特に育児を行う年代と、成果を上げ昇進や上位職獲得の足固めをする年代がオーバーラップするため、育児と家事を主に担う女性に「年齢を逃すと、将来の先がなくなる」ケースが頻発しています。このような研究者のジェンダーギャップを生み出す問題は、程度の差はあるにしてもほとんどの国や地域に普遍的に存在しており、現在も完全には解消されていません。ここでは、この問題の解決に積極的に取り組んできた事例として、米国の取り組みを紹介します。米国では1980年の科学技術機会均等法施行以降の20年間、女性研究者個人を支援する施策が続けられましたが女性研究者の割合が期待したほど伸びませんでした。それは、研究と家庭の両立が困難であることに加えて、女性研究者を排除する偏見と文化が組織に存在し、生き残った数少ない女性研究者には各種委員会の委員や教育などの業務が集中するという過酷な職場環境があり、女性研究者のキャリア追及の意思を挫いていたためでした。これらの問題を解決するためには、男女が平等にケア労働を担う意識変革と、ライフイベントと働き方(ワークライフバランス)に対する柔軟な対応を可能にする職場の意識とシステムの変革が必須です。そのため、2001年に米国科学アカデミーが「女性が能力をフルに発揮できる環境作り」、「女性自身による能力の開放」、「それを実現するための個人・システム・組織の改革」という3つの指針を作成し、アメリカ科学財団がADVANCEプログラムを立ち上げてこの指針にしたがって大学の組織変革を進めてきました。具体的には、ADVANCEは女性研究者やマイノリティー研究者を「可視化」し、「公正な登用」を可能にするための組織改革推進を目的として、システム改革、意識改革、ワークライフバランスを事業内容の中心として進められてきました。その結果、意識改革と組織変革がかなり進み、生命科学分野では研究者の女性割合が50%に到達し、物理、数学、工学分野でも女性研究者の割合が急勾配で上昇しています。
Q40
最近、夫婦別姓選択制の是非が話題になることが増えています。結婚により姓が変わることで、女性研究者のキャリア途絶につながると言われることがあります。一方で、旧姓併記によりキャリアの問題は解決可能との意見もあります。この問題についてどのように考えればいいのか、アドバイスを示していただきたいと思いました。
A40
“夫婦同氏制” に従って姓を変えた研究者のキャリア形成に関する不都合を完全には解決できないため、利便性の面から “選択的夫婦別姓(夫婦別姓選択制)” は必要です。研究者の場合は名前が看板であり、キャリアの途中で婚姻事情により姓が変わると過去の業績が自分の業績としてカウントされなくなる恐れがあります。特に、特許は戸籍名でしか登録が認められていないため、この問題を回避する手立てがありません。一方、論文では著者名に旧姓を使い続ける選択はできますが、そもそも姓が変わらなければそのような選択で悩む必要はないのです。国際的な活動をする場合にも、様々な不便が生じます。たとえば、パスポートの旅券面に旧姓・別姓が記載されていたとしても、ICチップには記録されません。ICチップに記載されている戸籍名と仕事に用いている旧姓が一致しないため、ビザの取得、航空券の購入・搭乗・入構等で非常に困るケースがでてきます。また、最初に海外で職を得た研究者は戸籍名以外でe-Radに登録できず、その後の研究費申請等で業績との齟齬が生じます。2023年に男女共同参画学協会連絡会が行った旧姓・通称使用に関する実態調査では、回答者(1713名)のうち12%が旧姓使用が理由で海外で不都合なことがあったと回答しています(https://www.djrenrakukai.org/request/juyoshiryo20240610.pdf)。
日本の “夫婦同氏制” は人権問題でもあります。現在、 “夫婦同氏制” を採用している国は世界で日本だけであり、国際連合はこれを規定した法律(民法750条)を1985年に日本が批准した「女子差別撤廃条約」に反した差別的な法規定としています。 2009年に国際連合の女子差別撤廃委員会から日本政府に出された「第6回報告に対する女子差別撤廃委員会の最終見解(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CEDAW6_co_j.pdf)」の差別的法規定に関する17項で、 “前回(2003年)の最終見解における勧告にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。” と指摘され、2016年に同委員会から配布された「日本の第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CO7-8_j.pdf)」で、 “女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること” が要請されています。さらに8年後の2024年に出された「第9回報告書の対する最終見解」(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_241030_e.pdf)でも、差別的な法律のセクションで “民法750条の改正の勧告が、特に対処されていないこと” が懸念を持って指摘され(最終見解11)、 “女性が結婚後も旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法律を改正する(最終見解12)” ことが勧告されています。
日本の “夫婦同氏制” は人権問題でもあります。現在、 “夫婦同氏制” を採用している国は世界で日本だけであり、国際連合はこれを規定した法律(民法750条)を1985年に日本が批准した「女子差別撤廃条約」に反した差別的な法規定としています。 2009年に国際連合の女子差別撤廃委員会から日本政府に出された「第6回報告に対する女子差別撤廃委員会の最終見解(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CEDAW6_co_j.pdf)」の差別的法規定に関する17項で、 “前回(2003年)の最終見解における勧告にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。” と指摘され、2016年に同委員会から配布された「日本の第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CO7-8_j.pdf)」で、 “女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること” が要請されています。さらに8年後の2024年に出された「第9回報告書の対する最終見解」(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_241030_e.pdf)でも、差別的な法律のセクションで “民法750条の改正の勧告が、特に対処されていないこと” が懸念を持って指摘され(最終見解11)、 “女性が結婚後も旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法律を改正する(最終見解12)” ことが勧告されています。
Q41
出版物の著者に女性がなりにくいというお話がありましたが、これはその研究に携わる女性研究者が補佐的な立場であることが多いこと等、バイアスの問題以外にも体制の問題によるところが大きいのではないかと思ったのですが、詳細な原因の解析はなされているかどうかが気になりました。
A41
2022年に発表された論文、「Women are Credited Less in Science than are Men」(Nature 608,135–145,2022)を紹介したスライドへのご質問ですね。この論文では、科学論文や特許の著者のジェンダーギャップ(著者に女性がなりにいこと)は、研究チーム内で女性の寄与が認められる可能性が男性よりも著しく低いことが原因の一つであることが証明されています。著者のジェンダーギャップは、従来は、女性が男性に比べて快適ではない職場環境で働いており、家族の責任が大きいこと、研究室での役職が異なること、または与えられる権限の種類が異なるために女性の生産性が低いことが原因であると考えられてきました。しかしこの論文では、2014年から2016年にかけて科学雑誌に掲載された39,426件の記事と7,675件の特許の著者である米国の9,778チームに属する128,859人の研究者を統計調査対象とし、ミシガン大学科学・イノベーション研究所が提供している36大学、118キャンパスの匿名化された人事管理データベースから明らかとなった全員の地位、助成金から支払われた給与情報をもとに各研究者が参加した研究プロジェクト情報も織り込んだ詳細な解析が行われました。その結果、労働時間、地位、分野、研究チームの特徴から生じるジェンダーギャップを補正しても、なおかつ著者のなりやすさに著しいジェンダーギャップが存在することが明らかにされました。そして、著者になる条件として、女性のほうが男性よりも高い貢献度を要求されていることが調査対象者へのアンケートから明らかにされ、この論文の図1(https://www.nature.com/articles/s41586-022-04966-w/figures/1)に示された著者のジェンダーギャップの大部分は、差別および貢献の評価方法に問題があることが示唆されています。この論文は、最も象徴的で悲劇的な例として、有名なワトソンとクリックのDNAの二重らせん構造の論文(Nature 171, 737–738,1953)からロザリンド・フランクリンの功績が無視され排除されていた事実を挙げており、約70年後の今日にいたっても、ロザリンド・フランクリンや過去の多くの女性科学者が遭遇したのと同様の差別が、科学の発展に大きな影響力を持つはずである多くの女性研究者の科学界への参入を妨げていると結論付けています。
Q42
スライドのPDFを一部でもいいので後日HP等で見ることができませんか?
A42
これまでの講演のスライドは、下記にすべて掲載されています。ご覧いただけると幸いです。
男女共同参画学協会連絡会
https://djrenrakukai.org
↓
無意識のバイアスコーナー
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/index.html
↓
講演
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/lecture.html
男女共同参画学協会連絡会
https://djrenrakukai.org
↓
無意識のバイアスコーナー
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/index.html
↓
講演
https://djrenrakukai.org/unconsciousbias/lecture.html